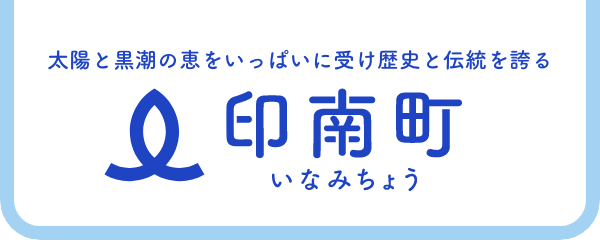障害者福祉
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:337
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
目次
1.身体障害者手帳
身体障害者(児)であることを証明するもので、各種の援護を受けるために必要なものです。
対象
上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸小腸、免疫機能等に障害があるため、日常生活に制限を受けている人。
申し込み
- 顔写真(縦3cm×横2.5cm)
- 指定された医師の診断書
※診断書の用紙は住民福祉課にあります。
2.療育手帳
知的障害者(児)の障害程度を把握し、各種の援護を受けるために必要なものです。
県子ども・障害者相談センター、児童相談所の判定が必要です。
申し込み
- 顔写真(縦3cm×横2.5cm)
- 18歳未満の場合は医師の診断書、18歳以上の場合は相談調査票
3.精神障害者保健福祉手帳
手帳を持つことで、一定の精神障害の状態にあることを証明する手段となり各種サービスを受けることができます。
障害の程度により、1~3級の手帳が交付され、有効期間は2年間です。
対象
精神疾患を有する人(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患のすべてが対象)のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人
手続きに必要なもの
- 申請
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 年金証書、年金振込通知書または医師による診断書
4.重度心身障害者福祉年金
日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳以上の重度心身障害者に、福祉年金を支給します。
受給資格
障害者であって本町に居住し、本町の住民票に記載されている者に対して次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
- 身体障害者手帳1級又は2級の者
- 療育手帳A1・A2の者
- 寝たきり等により、在宅看護を必要とするもの
支給額
療育手帳A1~A2、身体障害者手帳1~2級・・・・月額3,000円
申し込み
療育手帳または身体障害者手帳、金融機関預金口座番号が必要です。
5.心身障害児童福祉年金
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の心身障害児の保護者に、福祉年金を支給します。
受給資格
- 身体障害者手帳の交付を受けている者。
- 療育手帳の交付を受けている者。
支給額
療育手帳A1~B2、身体障害者手帳1~6級・・・・月額5,000円
申し込み
療育手帳または身体障害者手帳、診断書、金融機関預金口座番号が必要です。
6.特別障害者手当
重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の在宅の人に支給します。
支給額(令和7年度)
月額 29,590円(所得制限有)
申し込み
療育手帳または身体障害者手帳、診断書、金融機関預金口座番号が必要です。
※その他、細かい基準、所得制限があります。
7.障害児福祉手当
重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の人に支給します。
支給額(令和7年度)
月額 16,100円
申し込み
療育手帳または身体障害者手帳、診断書、金融機関預金口座番号が必要です。
※その他、細かい基準、所得制限があります。
8.障害者総合支援法
この法律は、これまでの障害者自立支援法に変わり、障害者及び障害児が、個人としての尊厳にふさわしい日常生活と社会生活を営めるよう、各種必要な障害福祉サービスで、統合的に支援を行えるよう、平成25年4月から施行されました。
利用に際し、事前に利用者の心身の状況を確認する「障害程度区分認定」を受ける必要があります。(住民福祉課までご相談ください。)
サービスの利用に対する費用負担は原則1割となります。ただし、支払の上限額や町民税が非課税の世帯については、さらに上限額を減額する減免の制度があります。
障害福祉サービスの一覧
訪問によるサービス
- 居宅介護(ホームヘルプ)
入浴や排泄、食事等自宅での生活全般にわたる介護を行います。 - 短期入所
介護者の急病などにより、自宅での介護ができない場合に短期間、施設内で生活上の介護を行います(宿泊を伴う場合) - 重度訪問介護
重度の肢体不自由がある人に、自宅内での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 - 行動援護
知的障害や精神障害により、行動が困難で常に介護を要する状況の人の外出時及び外出時前後の支援を行います。 - 重度障害者等包括支援
常時介護を要する人の中でも特に介護の必要性が高い人に居宅介護を含め他の障害福祉サービスを包括的に提供します。
日中活動のサービス
- 生活介護
常に介護を必要とされる人に、日中において、施設での食事、入浴等日常生活の支援や創作的、生産的活動の提供を行います。 - 療養介護
重症心身障害者等であって、長期入院による医療的な支援が必要な人に、病院等での入院による医学的管理の下で日常生活の支援や、身体機能訓練を提供します。 - 自立訓練
・身体障害者の人で地域生活を営む上での身体的リハビリテーションを提供します(機能訓練)
・知的障害・精神障害の人で日常生活能力を向上するための支援を提供します。(生活訓練) - 児童デイサービス
障害児に対して、施設に通っての日常生活における基本的な動作の指導や集団への適応訓練などを行います。
就労支援サービス
- 就労移行支援
就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上ための訓練や職場実習を一定期間の支援計画に基づき提供します。 - 就労継続支援
一般企業で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練の場を提供します。
居住系サービス
- 共同生活援助(グループホーム)
就労している又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者の人で、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助を行います。 - 施設入所支援
介護が必要な人、通所が困難な人で居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。
9.障害者日常生活用具費
障害者(児)の人の日常生活の便宜を図るための日常生活用具に係る費用の支給等を行います。
平成25年度より障害者手帳取得者以外で障害者総合支援法の難病の方も対象になります。
令和6年度から在宅透析に係る住宅改修及び機器の費用を支給対象に追加しました。
対象となる用具の一例
特殊寝台、入浴補助用具、ストマ用装具、点字器、頭部保護帽、パルスオキシメーター、ネブライザーなど
費用負担
原則1割負担となります。
※ただし、生活保護を受けている方、頭部保護帽の給付を受けた者、ストマ用装具の給付を受けた者については自己負担なしになります。
手続き
購入前に住民福祉課へ相談ください。なお、介護保険で給付や貸与ができる場合は、そちらが優先となります。
10.補装具費の支給
身体障害者の人の状況に応じ、日常生活の能率向上を図るための車いすや補聴器などの補装具の購入や修理にかかる費用を支給します。
介護保険等他の制度による貸与や給付が受けられる場合はそちらが優先となります。
平成25年度より障害者手帳取得者以外で障害者総合支援法の難病の方も対象になります。
手続き
補装具の種類によっては、県子ども・障害者相談センターでの判定や医師の意見書の作成が必要となることがありますので、事前に住民福祉課へご相談ください。
費用
購入や修理にかかる費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の住民税の課税状況により上限額があります。
市町村民税非課税世帯
- 月額上限額 0円
市町村民税課税世帯
- 月額上限額 37,200円
※市町村民税課税世帯のうち、世帯の生計中心者の町民税の所得割額が46万円を超える場合は、補装具費の支給対象外となります。
※令和6年4月1日から障害児の補装具費支給について、障害児本人又はその保護者等の所得割額が46万円を超える場合も補装具費の支給対象となります。
11.自立支援医療(精神通院医療)自己負担分助成
自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの方が指定自立支援医療機関に支払った通院医療費の自己負担額を助成します。
※診断書等の医療保険対象外費用は助成の対象となりません。
手続き
指定自立支援医療機関で発行された領収書と印かんをお持ちのうえ住民福祉課窓口で手続きしてください。
12.各種割引制度
有料道路通行料金の割引
対象範囲
- 身体障害者の方が自ら運転する場合
- 重度の身体障害者の方又は重度の知的障害者の方が同乗し、障害者本人以外の方が運転する場合(重度障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲)
令和5年3月27日より、これまで事前登録された自家用車に限り割引を適用となっていましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。
割引内容
原則として通常料金の半額
手続き
・ETCをご利用にならない場合
- 所定の申請書類(役場 住民福祉課にあります)
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 運転免許証
- 車検証(原本)
- 所定の申請書類(役場 住民福祉課にあります)
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 運転免許証
- 車検証(原本)
- ETCカード(障害者本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
- 84円切手 1枚
*詳しい内容は有料道路ETC割引登録係(電話045-477-1233)にお問い合わせください。
鉄道運賃の割引
対象範囲
身体障害者手帳及び療育手帳所持者に対して割引されます。
割引内容
- 第1種の割引
本人のみ乗車する場合は片道100kmを超える場合半額
(介護者と共に乗車する場合のみ片道100kmを超えない場合であっても両者半額) - 第2種の割引
本人のみ乗車する場合は片道100kmを超える場合半額
利用方法
各駅の窓口にて、身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、割引手続きを行ってください。
※詳しくは、各駅の窓口でお問い合わせください。
バス乗車運賃の割引
対象範囲
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者に対して割引されます。
割引内容
普通旅客運賃の5割引
利用方法
バス会社で身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示し、割引の手続きを行ってください。
※詳しくは、各バス会社にお問い合わせください。
タクシー運賃の割引
対象範囲
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者に対して割引されます。
割引内容
運賃の1割引
利用方法
タクシー会社で身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示し、割引の手続きを行ってください。
※詳しくは、各タクシー会社にお問い合わせください。
航空運賃の割引
対象範囲
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者に対して割引されます。
※詳しくは、航空会社・旅行会社でお問い合わせください。
NHK受信料の減免
対象範囲及び割引内容
- 半額免除
世帯主が視覚障害または聴覚障害による身体障害者手帳所持者又は重度の障害者(身体障害者手帳(1級又は2級)・知的障害者(療育手帳A1・A2)・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級))である場合 - 全額免除
身体障害者・知的障害者・精神障害者が世帯構成員であり、世帯全員が町民税非課税の場合
手続き
- 放送受信料免除申請書(役場 住民福祉課にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 認印
※審査後、証明を受けた申請書をNHKに提出してください。
お問い合わせ
印南町住民福祉課
電話: 0738-42-1738 ファックス: 0738-42-8020
電話番号のかけ間違いにご注意ください!