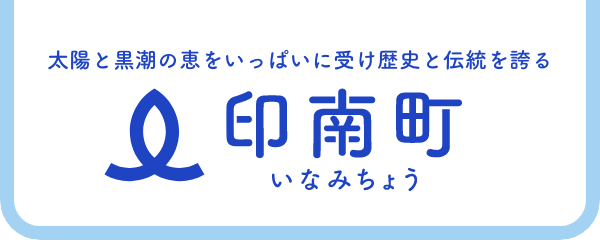食品ロスをなくしましょう
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1594
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
もったいない!! ~食品ロスをなくしましょう~
食品ロスとは、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことです。日本では令和3年度に約523万トンの食品ロスが発生したと推計されています。
そのうち、約半分の約244万トンが家庭から、残りの約279万トンは事業者から排出されています。食品ロスを国民一人当たりに換算すると"お茶碗約1杯分(約114g)の食べもの"が毎日捨てられていることになるのです。
大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品ロスを減らすことが必要です。
令和元年10月には「食品ロス削減推進法」が施行され、食品ロスの削減を総合的に推進することが規定されています。
(食品ロスの例)
・食べ切れずに廃棄される。(食べ残し)
・賞味期限切れ等により使用・提供されず、手つかずのまま廃棄される。(直接廃棄)
・野菜の皮などの食べられない部分を除去する際に、過剰に取り除かれた食べられる部分。(過剰除去)
家庭での取り組み
食品ロスを減らすために、次のことに気を付けましょう!
【買い過ぎない】
食材を買い過ぎたり、同じ食材を買ってしまったりすると、食材を使い切らずに廃棄してしまうことにつながります。
(取り組み例)
・買い物前に家にある食料品を確認する。
・買い物のリストを作成する。
・使い切れる量を購入する。
【保管方法を確認する】
保管方法を間違えると消費期限を待たずに廃棄することにつながります。
(取り組み例)
・食品ごとの保管方法を確認する。
・冷蔵庫の中を常に整理し、食品の種類や量を確認しやすくする。
・消費期限を確認しておく。
【作り過ぎない】
食事を作り過ぎると廃棄することにつながります。
(取り組み例)
・食べきれる量を把握し、作り過ぎない。
・使い切れなかった食材も適切に保管し、使い切る。
・残った料理もリメイクレシピを活用し、食べ切る。
生ごみの処理について(水切りをしましょう)
生ごみは、燃やせるごみの約35%を占めています。そのうち約80パーセントが水分です。
生ごみの水分をひと絞りするだけでごみが減量できるだけでなく、においや虫の発生も抑制できます。
印南町では生ごみの減量化・資源化を図るため、家庭用生ごみ処理機等を購入する方に補助金を交付しています → 詳しくはこちら
「賞味期限」と「消費期限」の違い
賞味期限と消費期限の違いは次のとおりです。
賞味期限は、「おいしく食べることができる期限」のことです。
期限が過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。
賞味期限を過ぎた食品は、見た目や臭いなどで、食べられるかどうかを個別に判断しましょう。
例)スナック菓子、カップ麺、缶詰、ペットボトル飲料など
【消費期限】
消費期限は、「安全に食べることができる期限」です。
期限を過ぎたら、食べない方がよいものです。
期限内に食べて、食品ロスを防ぎましょう。
例)弁当、サンドイッチ、ケーキなど
消費者庁:食品の期限表示に関する情報(外部リンク)
お問い合わせ
印南町生活環境課
電話: 0738-42-1732 ファックス: 0738-42-0175
電話番号のかけ間違いにご注意ください!