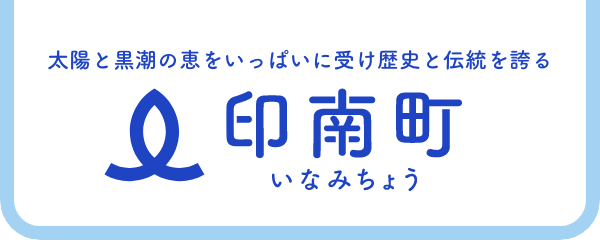清流小学校
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:210
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
清流小学校の紹介

校舎全景

正門
基本情報
- 住所
印南町羽六766 - 電話番号
0738-45-0001 - ファックス
0738-45-0924 - 通学区域
古屋・宮ノ前・羽六・古井・美里・樮川・松原・丹生・崎ノ原・小原・皆瀬川・田ノ垣内・西神ノ川・高串・上洞・川又
児童数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 2名 | 5名 | 2名 | 8名 | 2名 | 10名 | 29名 |
| 女子 | 4名 | 3名 | 7名 | 4名 | 3名 | 4名 | 25名 |
| 合計 | 6名 | 8名 | 9名 | 12名 | 5名 | 14名 | 54名 |
令和7年5月1日現在
沿革
清流小学校(印南町羽六766)
おもな出来事
- 平成21年(2009)4月
切目川・真妻・上洞の3小学校が統合し、清流小学校が誕生する。 - 平成24年(2012)7月
プールが完成する。 - 平成24年(2012)11月
緊急時地震速報端末を設置する。 - 平成25年(2013)5月
デマンド監視システムを設置する。 - 令和元年(2019)7月
普通教室、特別教室に空調設備を設置する。 - 令和元年(2019)9月
パソコン教室のパソコンを入れ替える。 - 令和2年(2020)10月
校内に無線LANを設置する。 - 令和2年(2020)12月
普通教室に電子黒板を導入する。 - 令和2年(2020)12月
児童1人1台の学習用端末を導入する。 - 令和2年(2020)12月
トイレ改修工事(洋式化)が完成する。
旧切目川小学校(印南町羽六766)
おもな出来事
- 明治8年(1875)8月
永福寺内に石川小学校が開校する。 - 明治11年(1878)5月
慶雲寺内に慶雲小学校が開校する。 - 明治16年(1883)8月
干害のために石川小学校が一時閉校するが、翌年8月、再び開校する。 - 明治20年(1887)1月
慶雲小学校が切畑に校舎を新築する。 - 明治20年(1887)4月
慶雲小学校が宮ノ前小学校と改称する。 - 明治33年(1900)8月
古井小学校が校舎を新築する(この頃、校名を石川から古井に変える)。 - 明治36年(1903)6月
宮ノ前小学校が校舎を新築する。 - 大正5年(1916)12月
古井小学校と宮ノ前小学校が合同の運動会を開く。 - 昭和4年(1929)1月
古井小学校と宮ノ前小学校が統合し、切目川小学校が開校する。 - 昭和9年(1934)9月
台風により校舎に被害が出る。 - 昭和17年(1942)8月
校舎を増築する。 - 昭和22年(1947)4月
新学制が施行される。 - 昭和23年(1948)4月
切目川小学校PTAを結成する。 - 昭和28年(1953)7月
切目川が氾濫し、運動場の一部、バックネット、鉄棒が流出する。 - 昭和29年(1954)8月
講堂が完成する。 - 昭和35年(1960)10月
完全給食を開始する。 - 昭和36年(1961)9月
第二室戸台風により講堂が倒壊する。 - 昭和38年(1963)8月
新講堂が完成する。 - 昭和63年(1988)5月
鉄筋二階建(一部三階建)の新校舎が完成する。 - 平成16年(2004)3月
新体育館が完成する。 - 平成18年(2006)4月
樮川小学校と統合する。 - 平成21年(2009)4月
真妻・上洞両小学校と統合し、当地において清流小学校として出発する。 - 平成24年(2012)7月
プールが新設される。
旧樮川小学校(印南町樮川690)
おもな出来事
- 明治9年(1876)3月
浄土寺を校舎に借用し、樮川小学校が開校する。 - 明治12年(1879)3月
藁葺の校舎を新築する。 - 明治31年(1898)4月
校舎を新築する。 - 明治40年(1907)4月
隣接する田畑を借り、運動場にあてる。 - 昭和5年(1930)4月
校舎を新築する。 - 昭和22年(1947)4月
新学制が施行される。 - 昭和23年(1948)7月
樮川小学校PTAを結成する。 - 昭和32年(1957)10月
完全給食を開始する。 - 昭和32年(1957)12月
講堂(へき地集会所兼用)を新築する。 - 昭和38年(1963)8月
運動場を拡張する。 - 昭和40年(1965)11月
校舎を増築する。 - 昭和48年(1973)7月
プールが完成する。 - 平成18年(2006)4月
切目川小学校と統合する。
旧真妻小学校(印南町皆瀬川227)
おもな出来事
- 明治11年(1878)11月
民家を借用し、崎ノ原小学校が開校する。 - 明治12年(1879)3月
空き家を借用し、小原小学校が開校する。 - 明治14年(1881)3月
崎ノ原小学校が民家の納屋を改修し、移転する。 - 明治15年(1882)4月
崎ノ原小学校が丹生大山に移転し、大山小学校と改称する。 - 明治18年(1885)6月
小原小学校が酒造を改修し、移転する。 - 明治19年(1886)1月
大山小学校が小原小学校を統合する。 - 明治19年(1886)11月
皆瀬川の民家を修繕のうえ移転し、皆瀬川尋常小学校と改称する。 - 明治25年(1892)5月
皆瀬川に校舎を新築する。 - 明治35年(1902)1月
真妻小学校と改称する。 - 明治35年(1902)9月
崎ノ原に校舎を新築する。 - 明治37年(1904)2月
小原に校舎を開設し、田ノ垣内・高串・小原・西神ノ川の児童を通わせる。 - 明治42年(1909)5月
小原の分教場を廃止し、本校に統合する。 - 大正元年(1912)9月
皆瀬川に校舎を新築、移転する。 - 昭和22年(1947)4月
新学制が施行される。 - 昭和23年(1948)2月
真妻小学校PTAが発足する。 - 昭和24年(1949)1月
校舎を新築する。 - 昭和24年(1949)12月
運動場を拡張する。 - 昭和29年(1954)1月
完全給食を開始する。 - 昭和38年(1963)12月
鉄筋三階建の新校舎と、木造の講堂(へき地集会所兼用)が完成する。 - 平成21年(2009)4月
切目川・上洞両小学校と統合し、清流小学校となる。
旧上洞小学校(印南町上洞807)
おもな出来事
- 明治12年(1879)1月
上洞・川又・高串3ヵ村を学区とする上洞村落小学校が開校する。 - 明治14年(1881)1月
明進小学校と改称する。 - 明治15年(1882)4月
川又村を学区として、親盛小学校が分立する。 - 明治18年(1885)5月
親盛小学校を統合し、上洞小学校と改称する。 - 明治19年(1886)10月
社会・経済的困難により、村崎訓導ら有志の尽力もかなわず閉校となる。 - 明治20年(1887)4月
上洞簡易小学校として再び開校する。また、川又小学校が分立する。 - 明治25年(1892)
川又小学校を統合し、上洞尋常小学校となる。 - 明治34年(1901)4月
高串を分割し、皆瀬川小学校区に編入する。 - 明治34年(1901)6月
校舎を新築する。 - 明治42年(1909)4月
高串を統合する。 - 大正3年(1914)8月
裁縫室を新築する。 - 昭和18年(1943)1月
校舎を新築する。村崎先生彰徳碑を除幕する。 - 昭和21年(1946)12月
南海大地震により、校舎西側の壁が落ちる。 - 昭和22年(1947)4月
新学制が施行される。 - 昭和23年(1948)5月
上洞小学校PTAを結成する。 - 昭和28年(1953)11月
完全給食を開始する。 - 昭和34年(1959)3月
講堂(へき地集会所兼用)が完成する。 - 平成21年(2009)4月
切目川・真妻両小学校と統合し、清流小学校となる。
令和7年度 教育方針
1.教育目標
知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな子どもの育成
2.具体目標
(1)確かな学力を身につけ、進んで学ぶ子どもを育てる。
- 基礎学力の身についた子
- 筋道を立てて考える子
- 自分の考えや思いを表現できる子
(2)思いやりのある子どもを育てる。
- 自分も友だちも大切にできる子
- 互いに認め合い、励まし合える子
(3)たくましく生きる子どもを育てる。
- 命や体を大切にする子
- 進んで運動をする子
- 食を大切にする子
- 粘り強く取り組む子
3.研究テーマ
「確かな学力を身につけ、自ら考え、共に学び合う子どもの育成」
(1)研究主題
主体的に学習に取り組む態度を育て、国語力を高める指導の工夫 ~国語科を通して~
(2)主題設定の理由
本校の児童は明るく素直で活発に生活し、課題に対しても前向きに粘り強く取り組んでいる。本校では、昨年度、「主体的に学習に取り組む態度を育て、問題解決能力を高める指導の工夫」の研究テーマのもと、「基礎基本の定着」「ICTの効果的活用」「表現力の育成」の3つの柱で研究を進めてきた。ICTの活用については、基礎学力の定着として、授業や家庭学習で、学習したことを一斉に、または児童の関心や進度に応じて等、さまざまな形でドリル等の活用を行い、学力の定着に努めた。さらに、表現力の育成に向けて、相手意識を大切にしながら自分の考えをまとめたり、課題に応じて作品を作ったりする活動も積極的に取り入れた。ICTを使ってお互いの意見や作品に触れ、その良さを伝えたり、自分に取り入れたりという面で、効果を上げることができた。しかし、自分の考えを発表したり、書いたり、また相手と意見を話し合ったりするといった力には、まだまだ課題が見られる。それらの力を育てていくためには、まず下地となる国語力を充実させていくことが大切であると考える。
そこで,今年度は研究主題を「主体的に学習に取り組む態度を育て,国語力を高める指導の工夫~国語科を通して~」と設定し,2つの柱をもとに研究主題の達成に取り組んでいく。
1つ目は,「基礎基本の定着」である。新たな問題や応用的な問題に直面したとき,既存の知識から想像力を働かせ,その解決に向かうことは,主体的に学習に取り組み,問題解決をしていく上で,基礎基本の定着はなくてはならない要素である。日々の授業はもちろん、朝の基礎学タイム(わかあゆタイム)での,漢字や言葉の学習などを続け,個々の弱点を補習しながら子どもの実態に応じた指導を進めることで基礎基本の定着をはかっていきたい。
2つ目の柱は,「語彙力獲得へのアプローチ」である。研究の1年目となる今年度は,主に音読や視写の取り組みから語彙力の獲得にアプローチしていく。言葉のまとまりや文の構成を把握するためにも音読や視写は効果的であり,学年に応じた形で取り組んでいく。それとともに,日々の読書活動にも意識して取り組むようにする。さらに,児童自身がより主体的に取り組めるように,普段の生活体験や行事など身近に感じることができる体験的活動と結びついた試みを行っていく。
“子どもの主体性は「楽しさ」から生まれる”という考えをもとに,子どもたち自身が学ぶ楽しさを感じ,本質的な基礎基本の定着を図りながら,主体的に学習に取り組むことができるような授業の展開を研究していく。
お問い合わせ
印南町教育委員会
電話: 0738-42-1700 ファックス: 0738-42-1577
電話番号のかけ間違いにご注意ください!