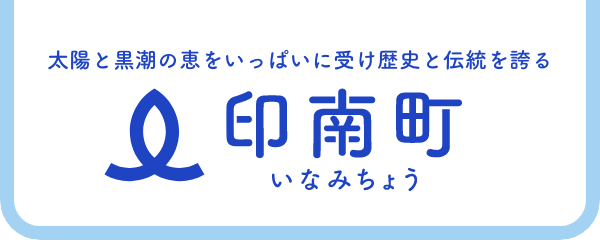印南中学校
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:225
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
印南中学校の紹介

校舎全景

正面玄関
基本情報
- 住 所 印南町印南2145
- 電話番号 0738-42-0021
- ファックス 0738-42-1042
- メールアドレス inami-j@wakayama-inami.ed.jp
- 通学区域 津井、印南、山口
生徒数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 11名 | 6名 | 16名 | 33名 |
| 女子 | 14名 | 9名 | 14名 | 37名 |
| 合計 | 25名 | 15名 | 30名 | 70名 |
令和7年5月1日現在
沿革
印南中学校(印南町印南2145)
おもな出来事
- 昭和22年(1947)5月
印南中学校が開校する。 - 昭和22年(1947)10月
印南中学校PTAを結成する。 - 昭和23年(1948)8月
校舎を新築する。 - 昭和25年(1950)8月
スタンドのコンクリート工事を行う。 - 昭和28年(1953)7月
校歌を制定する。 - 昭和31年(1956)4月
校舎を新築する。 - 昭和32年(1957)10月
運動場で初めての運動会を開催する。 - 昭和35年(1960)7月
運動場を拡張する。 - 昭和36年(1961)2月
校門が完成する。 - 昭和36年(1961)11月
教室を増築する。 - 昭和38年(1963)12月
健康優良学校として県から表彰される。 - 昭和40年(1965)10月
完全給食を開始する。 - 昭和41年(1966)5月
体育館が完成する。 - 昭和44年(1969)8月
運動場を拡張する。 - 昭和57年(1982)2月
県スポーツ賞を受賞する。 - 昭和57年(1982)3月
全日本造形教育作品優秀校賞と全日本英語検定優秀校賞を受賞する。 - 平成5年(1993)9月
校舎・体育館を新築する。 - 平成9年(1997)5月
開校50周年記念式典を挙行する。 - 平成13年(2001)3月
体育館南側に校歌歌碑を設置する。 - 平成13年(2001)12月
生徒会活動でジャンボ年賀状の取り組みが始まる。 - 平成19年(2007)12月
選択理科で「つなみ」研究、全日本学生科学賞に入選する。 - 平成20年(2008)11月
平成20年度文科学省・和歌山県教育委員会指定、全国学力・学習状況調査等を活用した学校改善の推進に係る実践研究発表会を行う。 - 平成20年(2008)12月
「つなみ」研究、全日本学生科学賞に入選、県知事賞を受賞する。 - 平成21年(2009)12月
「つなみ」研究、県知事賞を受賞する。 - 平成24年(2012)11月
緊急時地震速報端末を設置する。 - 平成25年(2013)5月
デマンド監視システムを設置する。 - 平成27年(2015)4月
アクサユネスコ防災減災学校に指定される。 - 平成28年(2016)4月
平成28年度ジュニアハイスクール指定事業(ソフトテニス男子・ソフトテニス女子)指定 - 平成28年(2016)6月
空調設備を設置する。 - 平成28年(2016)8月
ソフトテニス部女子団体・個人全国大会出場 - 平成29年(2017)1月
1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」優秀賞受賞 - 平成29年(2017)1月
ふるさとわかやま学習大賞受賞 - 平成29年(2017)4月
平成29年度ジュニアハイスクール指定事業(ソフトテニス男子・ソフトテニス女子)指定 - 平成30年(2018)1月
1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」1.17防災未来賞受賞 - 平成31年(2019)1月
ふるさとわかやま学習大賞 大賞受賞 - 令和2年(2020)10月
校内に無線LANを設置する。 - 令和2年(2020)12月
普通教室に電子黒板を導入する。 - 令和2年(2020)12月
生徒1人1台の学習用端末を導入する。 - 令和2年(2020)1月
1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」奨励賞 - 令和3年(2021)1月
1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」ぼうさい大賞受賞 - 令和4年(2022)1月
1.17防災未来賞「ぼうさい甲子園」URレジリエンス賞受賞
令和7年度 教育方針
1.教育目標
未来を切り拓くための「確かな学力」「豊かな心」「たくましい体」を育成する
2.めざす学校像
- 生徒が行きたい学校
- 保護者が行かせたい学校
- 地域住民が誇れる学校
3.めざす生徒像
- すすんで挨拶ができ、人の気持ちがわかる生徒
- よく考え、正しく判断し、自主的・意欲的に行動する生徒
- 学習と部活動ともに忍耐強く励む生徒
- 家庭・地域での生活を大切にし、節度ある社会性を身につけた生徒
4. めざす教職員像
- 人間的な魅力にあふれ、夢と情熱をもった教職員
- 生徒を認め、ほめ、励まし、伸ばす教職員
- 課題解決に向けて組織的に協力・協働できる教職員
- 変化を前向きに受けとめ、学び続ける教職員
5.教育目標達成への教育基盤と重点項目
(1)教育基盤
- 相互信頼と共通理解による人間関係を基盤とした運営体制(報告・連絡・相談)
- 適正な教育課程による計画的・能率的な学校運営
- 地域と一体となって子供を育む「地域とともにある学校」
- 伝統の継承、望ましい校風の樹立
- 園小中連携(義務教育12ヶ年事業)
(2)重点項目
①確かな学力の向上
- 『和歌山の授業づくり 基礎・基本 3か条 第二版』の徹底
- 学習者用デジタル教科書等のICT活用による学びの質の向上
- 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な実現
- 言語活動を大切にする学習の展開(書く、読む、伝える)
- 学校図書館を核にする読書活動の推進
- 特別支援教育の充実
②豊かな心の育成
- 特別の教科道徳の充実
- 地域行事やボランティア活動への参加
- 体験活動の充実
- 生徒会活動の活性化により望ましい人間関係形成
③たくましい体の育成
- 基本的な生活習慣の確立
- 『印南町運動部活動の方針』に基づく効果的・効率的な部活動運営
- 自校調理による学校給食の実施と食育の推進
- 地域や関係機関と連携した防災教育
- キャリア教育の視点に立つ教育活動
6.研究主題
「全ての生徒の可能性を引き出す学びの創造」
7.主題設定の理由
これまで本校では、全国学力・学習状況調査、標準学力調査、県学習到達度調査等の結果を分析・活用した授業改善に継続して取り組み、生徒がどの授業でも安心して学びに向かえるように、「和歌山の授業づくり 基礎・基本 3か条」及び同第二版をもとに全教員で「授業スタイル」の統一を進めてきた。そして、令和3年度から学習者用端末等も活用して、全ての教科で「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の研究を進め、実践を通して成果及び課題を見いだしてきた。
本校の生徒は、授業では意欲的に学習に取り組めているものの、学習内容を十分に定着できない生徒もみられる。そこで、昨年度に「全ての生徒の可能性を引き出す学びの探究」を主題として研究を進めてきたことを引き継ぎ、今年度は「全ての生徒の可能性を引き出す学びの創造」を目指していく。そして、その中でこれまでの実践とICTを最適に組み合わせて授業の質を高め、全ての教科・領域等で「主体的・対話的で深い学び」を充実させる。このようにして生徒に「生きる力」の育成を図りたい。
その他の情報
お問い合わせ
印南町教育委員会
電話: 0738-42-1700 ファックス: 0738-42-1577
電話番号のかけ間違いにご注意ください!